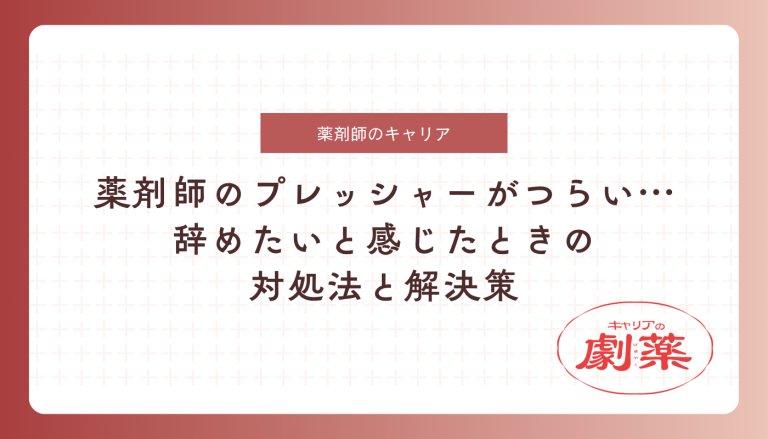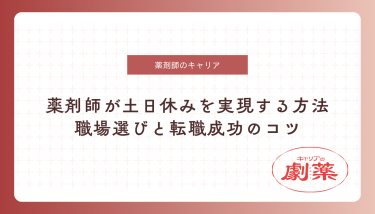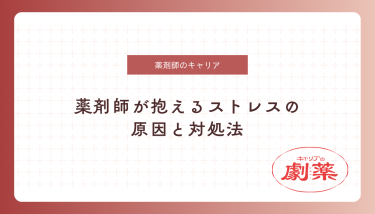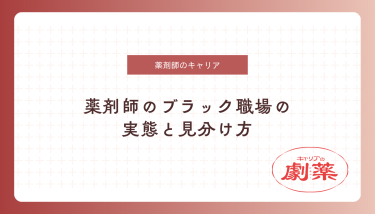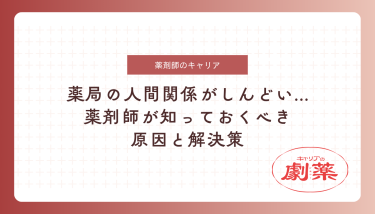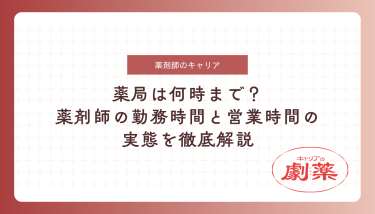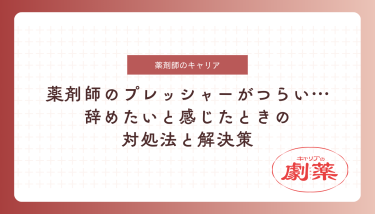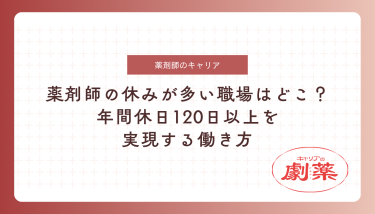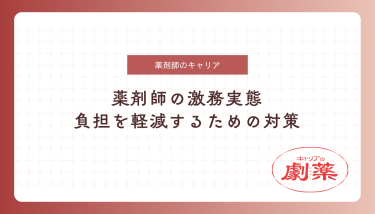薬剤師として働く中で、調剤ミスへの不安や人間関係のストレス、業務量の多さから「もう限界かもしれない」と感じていませんか。実は医療・福祉業界の離職率は15.3%で、約3人に1人の薬剤師が3年以内に職場を離れています。
本記事では、プレッシャーに苦しむ薬剤師の方に向けて、具体的な対処法と環境を変えるための選択肢を解説します。
薬剤師がプレッシャーを感じる5つの主な原因
薬剤師の仕事には、他の職種とは異なる独特のプレッシャーが存在します。ここでは、多くの薬剤師が抱える代表的なストレス要因を詳しく見ていきましょう。
調剤ミスへの強い責任とプレッシャー
薬剤師の業務で最も大きなプレッシャーとなるのが、調剤ミスに対する不安です。薬の取り違えや数量間違いは患者さんの命に直結する可能性があり、一つのミスも許されない緊張感の中で働き続けることになります。
公益財団法人日本医療機能評価機構の報告によると、2014年には薬局から5,399件のヒヤリ・ハット事例が報告されており、午前10時から正午の混雑時間帯に発生率が高まることが分かっています。
出典:公益財団法人日本医療機能評価機構
調剤過誤が発生した場合、薬剤師は刑事責任(業務上過失致死傷罪)、行政責任(免許取消・業務停止)、民事責任(損害賠償)の3つの法的責任を問われる可能性があります。このような重い責任感が、日々の業務に大きなプレッシャーをもたらしています。
人間関係の悩みと閉鎖的な職場環境
薬剤師の職場は、調剤薬局では約7割が3人以下、病院でも約7割が10人以下という少人数体制です。この閉鎖的な環境では、一人でも相性の合わない同僚や上司がいると、逃げ場がなく大きなストレスとなります。
調剤室という狭い空間で、同じメンバーと長時間過ごすため、人間関係がこじれると仕事そのものが苦痛になってしまいます。特に以下のような状況では、プレッシャーが増大します。
・パワハラやモラハラを受けている
・先輩や上司に相談しづらい雰囲気がある
・チーム内でのコミュニケーション不足
・医師や看護師との連携で気を遣う場面が多い
薬剤師は「感情労働」と呼ばれる職種の一つで、自分の感情を抑制して患者さんや医療従事者と接する必要があるため、精神的な疲労が蓄積しやすい特徴があります。
人手不足による過重労働と業務量の増加
病院薬剤師の離職率は5%未満が約半数である一方で、人手不足が深刻化している職場では、一人あたりの業務負担が大きくなっています。
出典:厚生労働科学研究成果データベース「病院における薬剤師の働き方の実態を踏まえた生産性の向上と薬剤師業務のあり方に関する研究」
薬剤師が1日に応需できる処方箋枚数は基本的に40枚までとされていますが、処方箋の内容によっては40枚に近い数字でも業務負担は非常に大きくなります。さらに、薬歴記入や在庫管理などの付随業務も含めると、残業が常態化している職場も少なくありません。
人手不足の職場では以下のような問題が発生します。
・有給休暇を取りにくい雰囲気
・残業が多く、プライベート時間が確保できない
・休憩時間もままならない
・一人薬剤師として責任が重すぎる
患者さんからのクレームや理不尽な対応
服薬指導や窓口業務では、患者さんとのコミュニケーションが不可欠ですが、時には理不尽なクレームや心ない言葉を受けることもあります。
・「待ち時間が長すぎる」と怒られる
・在庫がないことを伝えると「何も置いていない薬局」と非難される
・薬の副作用について説明すると不機嫌になる
・薬剤師の対応を毛嫌いする患者さんもいる
患者さんの年齢や性格、症状によって対応を変えなければならず、感情労働としてのストレスが大きい業務です。真面目で責任感の強い薬剤師ほど、患者さんからの言葉を深く受け止めてしまい、心が疲弊していきます。
給与や待遇への不満
薬剤師の平均年収は日本の平均年収より高い水準にありますが、6年制の教育課程を経て得られる専門資格であることや、背負う責任の重さを考慮すると、必ずしも満足できる水準ではないと感じる薬剤師も多くいます。
特に以下のような状況では、給与への不満が離職につながりやすくなります。
・勤続年数を重ねても昇給がほとんどない
・サービス残業が常態化している
・管理薬剤師になっても手当が少ない
・退職金制度が整備されていない
また、病院薬剤師と薬局薬剤師では、20〜30代の年収に差があり、薬局薬剤師の方が年収が高い傾向にあります。このような給与格差も、転職を考えるきっかけになっています。
出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査」
プレッシャーで「辞めたい」と思ったときの自己診断チェック
すぐに退職を決断する前に、まず自分の状態を客観的に見つめ直すことが大切です。以下のチェックリストで、現在の状況を確認してみましょう。
今すぐ環境を変えるべきサイン
以下に該当する項目が多い場合は、早急に環境を変えることを検討すべきです。
□ 朝起きると体が重く、出勤するのが憂鬱で仕方がない
□ 不眠や食欲不振が続いている(5〜6日以上)
□ 職場のことを考えると動悸や息苦しさを感じる □ 集中力が低下し、ミスが増えている
□ 誰にも相談できず、孤立していると感じる
□ パワハラやモラハラを受けている □ 体調不良で欠勤することが増えた
これらの症状が続く場合は、メンタルヘルスの不調のサインかもしれません。専門医への受診や、休職・退職も視野に入れる必要があります。
まだ改善の余地がある場合のサイン
以下の項目に該当する場合は、職場環境の改善や働き方の見直しで状況が好転する可能性があります。
□ 特定の業務や時間帯だけストレスを感じる
□ 上司や同僚に相談できる人がいる
□ プライベートでは気分転換ができている
□ 薬剤師の仕事自体にはやりがいを感じている
□ 経験を積めば改善できそうな悩みである
この場合は、次に紹介する対処法を試してみることをおすすめします。
プレッシャーを軽減するための具体的な対処法
辞める前に試せる、プレッシャーを軽減するための実践的な方法を紹介します。
信頼できる人に相談する
一人で悩みを抱え込まず、信頼できる人に話を聞いてもらうことが第一歩です。職場の先輩や上司、同期、あるいは友人や家族でも構いません。
客観的な意見をもらうことで、冷静に状況を判断できるようになります。また、上司に相談することで、配置転換やシフト調整など、職場環境の改善につながることもあります。
業務改善の提案をする
職場環境が原因で悩んでいる場合は、思い切って上司に業務改善の提案をしてみましょう。以下のような改善項目を具体的にまとめて提案することが効果的です。
・調剤監査システムの導入
・ダブルチェック体制の強化
・業務マニュアルの整備
・シフトの見直し
・人員配置の最適化
大切なのは、結果よりも「改善に向けて行動した」という過程です。この経験は、今後のキャリアにおいても貴重な学びとなります。
ストレスコーピングの実践
ストレスコーピングとは、ストレスに対処するための行動や考え方のことです。以下の2種類のアプローチを状況に応じて使い分けることが効果的です。
問題焦点型コーピング:問題の原因に直接アプローチして解決する方法
・業務の優先順位を明確にする
・タスク管理ツールを活用する
・疑義照会のタイミングを工夫する
情動焦点型コーピング:感情をコントロールして気持ちを落ち着かせる方法
・深呼吸やマインドフルネス瞑想(5分程度でも効果的)
・適度な運動(15分のウォーキングでも効果あり)
・趣味や好きなことに没頭する時間を作る
愛知県内の在宅医療に携わる薬剤師266名を対象にした調査では、女性および終末期患者の対応経験がある薬剤師は、これら2つのコーピングを柔軟に活用していることが明らかになっています。
出典:日本薬局学会誌「在宅医療における薬剤師のストレスコーピングの現状」
働き方を見直す
正社員からパートやアルバイトへの雇用形態変更、勤務時間の短縮など、働き方を柔軟に見直すことでプレッシャーを軽減できる場合があります。
・週3日勤務に変更する
・時短勤務を申し出る
・派遣薬剤師として働く
・調剤以外の業務(製薬会社、CRC・CRAなど)を検討する
転職を成功させるためのポイント
環境を変えることを決断した場合、後悔のない転職をするためのポイントを押さえておきましょう。
離職率の低い職場の見極め方
大規模チェーンでは転勤が頻繁にあり、離職率が高くなる傾向があります。一方で、小規模薬局では人間関係が固定化しやすいという側面もあるため、自分の性格や希望に合った職場を選ぶことが大切です。
確認すべき職場環境のポイント
求人情報や面接では、以下の点を具体的に確認しましょう。
・一人あたりの1日の処方箋応需枚数(40枚に近い場合は要注意)
・薬剤師の配置人数と勤務シフト
・残業時間の実態
・有給休暇の取得率
・調剤監査システムの導入状況
・研修制度やキャリアアップ支援
・転勤の有無と頻度
転職時期とタイミング
薬剤師3年目以降の転職が有利とされています。採用側は「3年以上の経験があれば即戦力」と判断する傾向があるためです。
ただし、心身の健康を損なうほどの状況であれば、年数にこだわらず早めに環境を変えることを優先すべきです。健康を取り戻してから、じっくりと次のキャリアを考える方が建設的です。
転職エージェントの活用
薬剤師専門の転職エージェントを利用することで、以下のメリットがあります。
・非公開求人へのアクセス
・職場の内部情報の提供
・給与交渉のサポート
・履歴書・面接対策
・退職手続きのアドバイス
特に初めての転職では、プロのサポートを受けることで、より自分に合った職場を見つけやすくなります。
薬剤師を辞める前に考えるべきこと
「薬剤師そのものを辞めたい」と考えている場合でも、一度立ち止まって考えてみましょう。
薬剤師資格を活かせる多様な働き方
調剤業務から離れても、薬剤師資格を活かせる仕事は多数あります。
・企業薬剤師:製薬会社、医薬品卸、医療機器メーカー
・CRC(治験コーディネーター)・CRA(臨床開発モニター):裏方業務が中心でプレッシャーが少ない
・医薬品情報担当者(DI)
・学校薬剤師
・薬事申請業務
・医療ライター
これらの職種では、調剤のプレッシャーから解放され、薬剤師としての知識を別の形で活かすことができます。
一時的な休職の検討
すぐに退職せず、まずは休職制度を利用して心身を休めることも選択肢の一つです。有給休暇を消化したり、医師の診断書をもとに休職したりすることで、冷静に今後のキャリアを考える時間が得られます。
体調を万全にしてから、改めて「本当に辞めるべきか」「環境を変えれば続けられるか」を判断しても遅くはありません。
よくある質問(FAQ)
- Qプレッシャーに耐えられないのは甘えでしょうか?
- Aいいえ、決して甘えではありません。薬剤師の業務は人の命に関わる責任の重い仕事であり、強いプレッシャーを感じるのは当然です。「辞めたい」と感じることは、心身からの重要なサインです。真面目で責任感が強い人ほど自分を追い込みがちですが、まずは自分の心と体を大切にしてください。
- Q新人薬剤師ですが、もう辞めたいと思っています。早すぎますか?
- A新人だからこそ感じるプレッシャーもあります。経験を積むことで解決する悩みなのか、職場環境に問題があるのかを見極めることが重要です。体調を崩すほど追い込まれているなら、早めに環境を変えることも必要です。ただし、3年程度の経験があると転職時に有利になるため、可能であれば信頼できる先輩に相談しながら、もう少し頑張ってみる選択肢も検討してみてください。
- Q転職回数が多いと不利になりますか?
- A薬剤師の転職は比較的一般的で、一般的な勤続年数以上の経験があれば早期退職とは判断されにくい傾向があります。重要なのは「なぜ転職したのか」を明確に説明できることです。面接では、前向きな理由として伝えられるよう準備しましょう。
- Q薬剤師を完全に辞めて、別の仕事に就くことはできますか?
- A可能です。ただし、6年間学んだ専門知識と資格は大きな財産です。調剤以外でも薬剤師資格を活かせる仕事は多数あるため、まずはそちらを検討することをおすすめします。それでも別の道を選びたい場合は、自分が本当にやりたいことを見極めてから決断しましょう。
- Qプレッシャーに強くなる方法はありますか?
- A完璧主義を手放し、「ミスは誰にでも起こりうる」という前提で対策を考えることが大切です。調剤監査システムの活用、ダブルチェック体制、疑義照会の徹底など、システムでミスを防ぐ環境を整えることで、個人にかかるプレッシャーを軽減できます。また、ストレスコーピングを実践し、仕事とプライベートのメリハリをつけることも効果的です。
まとめ
薬剤師のプレッシャーは、調剤ミスへの不安、人間関係、過重労働、患者対応、給与の不満など多岐にわたります。心身の限界を感じている場合は、休職や退職も選択肢です。
まだ改善の余地がある場合は、相談や業務改善、ストレスコーピング、働き方の見直しを試してみましょう。転職を考える際は、離職率の低い職場を見極め、専門エージェントの活用も検討してください。
何より大切なのは、あなた自身の心と体です。一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に相談しながら、最適な選択をしてください。
まずはキャリアの可能性を知る相談から
キャリア相談・面談依頼はこちらから
田井 靖人
2013年摂南大学法学部を卒業後、不動産業界で土地活用事業に従事。
2019年から医療人材業界へ転身し、薬剤師と医療機関双方に寄り添う採用支援に携わる。
現在は薬剤師が“自分らしく働ける環境”を広げるべく、現場のリアルやキャリアのヒントを発信。 座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。どんな経験も糧に変え、薬剤師の未来を支える言葉を届けている。