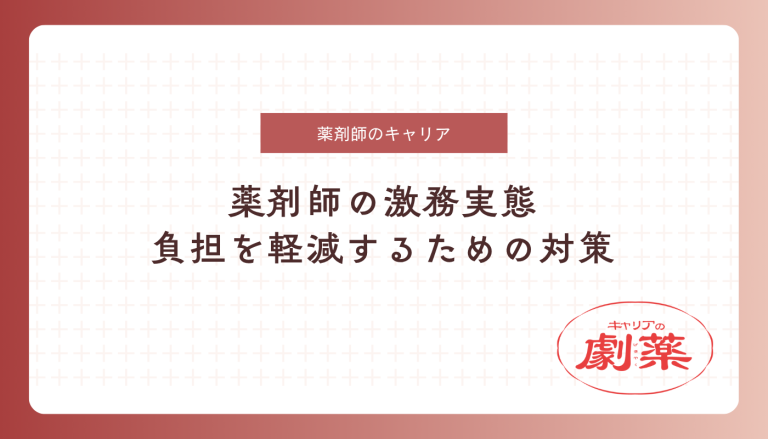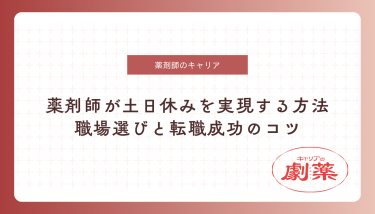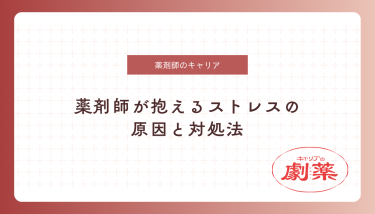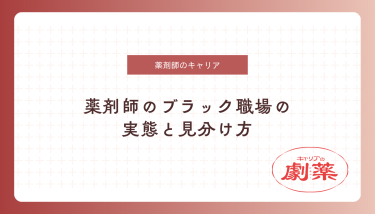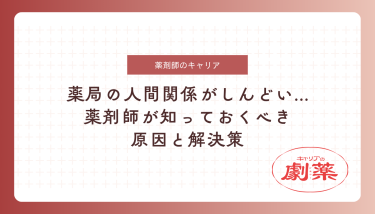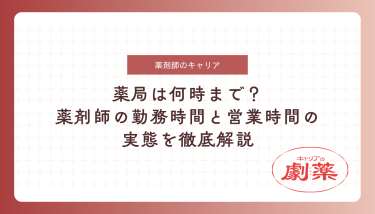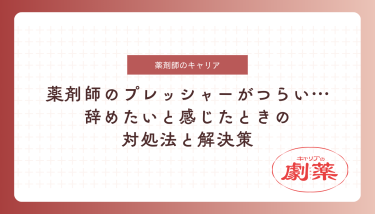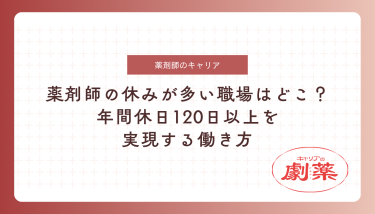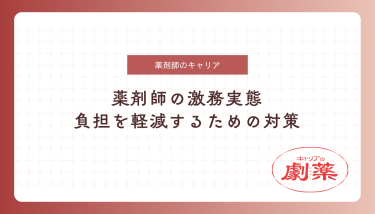「薬剤師は激務」この言葉を実感している薬剤師は少なくありません。厚生労働省の調査によると、薬剤師の所定外労働時間は月平均10時間前後ですが、これは申告ベースであり、実際にはサービス残業を含めるとさらに多いのが現実です。
本記事では、薬剤師専門のキャリアアドバイザーとして多数の相談を受けてきた経験から、激務の実態、健康への影響、そして負担を軽減するための具体的な対策を解説します。
薬剤師の激務が深刻化している5つの背景
薬剤師の激務には構造的な要因があります。業務量の増加、人員不足、多様な業務の並行処理など、複数の要因が重なり合って激務状態を生み出しています。
業務量の増加と処方箋枚数の急増
厚生労働省「薬局機能情報提供制度」によると、1薬局あたりの月平均取扱処方箋枚数は増加傾向にあります。高齢化社会の進展により、薬局を訪れる患者数は年々増加しており、薬剤師一人当たりの業務負担が重くなっています。
特に大型病院の門前薬局では、1日に300枚以上の処方箋を扱うケースもあり、薬剤師は休憩時間もままならない状況で働いています。
深刻な人員不足
厚生労働省「令和2年(2020)医療施設(動態)調査・病院報告の概況」によると、薬局の従業者数は平均4.4人と小規模です。
出典:厚生労働省「令和2年(2020)医療施設(動態)調査・病院報告の概況」
薬剤師の採用難が続く中、既存スタッフの負担が増加しています。一人が退職すると、残された薬剤師の業務量が急増し、さらに離職者が出るという悪循環が生じています。
多様化する業務内容
従来の調剤業務に加えて、以下のような業務が増加しています。
対人業務の強化: 服薬指導、薬歴管理、残薬確認
在宅医療への対応: 訪問服薬指導、医療介護連携
かかりつけ薬剤師業務: 24時間対応、継続的な患者フォロー
OTC医薬品販売と健康相談: セルフメディケーション支援
医療安全管理: 疑義照会、副作用モニタリング
これらの業務を限られた時間内でこなすことが、激務の大きな要因となっています。
調剤報酬改定による経営圧力
調剤報酬の改定により、薬局の収益構造が変化しています。経営効率化の圧力が高まる中、人員を増やすことが難しく、既存スタッフの業務負担が増加しています。
患者対応の複雑化
高齢患者の増加、多剤併用、ジェネリック医薬品の説明、クレーム対応など、患者対応に要する時間と労力が増加しています。丁寧な説明を求められる一方、待ち時間短縮も求められるという板挟みの状況が、薬剤師のストレスを高めています。
職場別:薬剤師の激務実態
調剤薬局、病院、ドラッグストアなど、働く環境によって激務の内容や程度は異なります。それぞれの職場での具体的な激務状況を理解することで、自分の状況を客観的に把握できます。
調剤薬局の激務実態
【典型的な1日のスケジュール】
8:30 出勤・開店準備(在庫確認、機器点検)
9:00 開局・処方箋受付開始
9:00-12:00 午前のピーク(処方箋が集中)
12:00-13:00 昼休み(取れないことも多い)
13:00-18:00 午後の業務
18:00-19:00 夕方のピーク
19:00 閉局・後片付け
19:00-20:00 レセプト業務、在庫管理、薬歴記載
【激務のポイント】
午前11時〜12時の処方箋集中により休憩が取れない
疑義照会で医師との連絡に時間がかかる
閉局後の事務作業で帰宅が遅くなる
月末月初のレセプト業務で残業が増加
病院薬剤部の激務実態
【病院特有の激務要因】
夜勤・当番制: 24時間体制での対応が必要
緊急対応: 救急患者への迅速な対応
高度な専門業務: がん化学療法の調製、無菌調製
病棟業務: カンファレンス参加、服薬指導
学術活動: 勉強会、論文作成、学会発表
【夜勤の負担】
夜勤は月4〜5回程度が一般的ですが、生活リズムの乱れから体調を崩す薬剤師も少なくありません。夜勤明けの疲労が蓄積し、慢性的な睡眠不足に陥るケースがあります。
ドラッグストアの激務実態
【ドラッグストア特有の激務要因】
長時間営業: 朝9時〜夜10時、11時まで営業
シフト制の不規則さ: 早番・遅番の切り替えで生活リズムが乱れる
調剤以外の業務: 品出し、レジ対応、売上管理
繁忙期の激務: 年末年始、ゴールデンウィークの休めない状況
人員不足: 薬剤師一人体制の時間帯
薬剤師の激務が及ぼす深刻な健康被害
長時間労働と過重な業務負担は、薬剤師の心身の健康に深刻な影響を与えます。厚生労働省の調査や医療従事者の健康に関する研究から、激務が引き起こす問題を解説します。
身体的な健康被害
【よくある症状】
慢性的な疲労: 休んでも疲れが取れない状態が続く
睡眠障害: 不眠、浅い眠り、中途覚醒
頭痛・肩こり: デスクワークと立ち仕事の組み合わせによる身体的負担
胃腸障害: ストレス性の胃痛、食欲不振
免疫力低下: 風邪を引きやすくなる
メンタルヘルスへの影響
【精神的症状】 厚生労働省「労働安全衛生調査」によると、強いストレスを感じる労働者の割合は高い水準で推移しています。
出典:厚生労働省「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)」
【薬剤師の激務がもたらす精神的影響】
抑うつ症状: 気分の落ち込み、意欲の低下
不安障害: 常に緊張状態、パニック症状
バーンアウト: 燃え尽き症候群、仕事への無関心
イライラ・怒りっぽさ: 些細なことで感情的になる
医療安全への影響
疲労が蓄積すると、集中力が低下し、調剤ミスのリスクが高まります。激務は薬剤師個人の問題だけでなく、患者の安全にも直結する重要な問題です。
離職リスクの増大
激務が続くと、離職を選択する薬剤師が増えます。離職により人員不足がさらに深刻化し、残されたスタッフの負担が増すという悪循環が生じます。
【実践編】薬剤師の激務を軽減する7つの対策
人間関係の改善には、自分自身のアプローチを変えることが最も効果的です。相手を変えようとするのではなく、自分にできることから始めることで、状況は好転します。
対策1:業務の優先順位付けとタスク管理
全ての業務を完璧にこなそうとせず、優先順位を明確にすることが重要です。
【実践方法】
緊急度と重要度のマトリクス活用: 業務を4つに分類(緊急×重要、緊急×非重要、非緊急×重要、非緊急×非重要)
「緊急×重要」を最優先: 処方箋調剤、疑義照会、患者対応
「非緊急×非重要」は後回し: 細かな整理整頓、完璧な記録
To-Doリストの活用: 翌日の業務を前日に整理
対策2:業務の効率化とデジタルツールの活用
【効率化のポイント】
調剤支援システムの活用: バーコード照合、自動分包機
薬歴記載の効率化: テンプレート活用、音声入力
疑義照会の効率化: FAX・メール活用、記録の標準化
在庫管理の自動化: 発注システムの活用
対策3:業務分担の見直しと役割の明確化
薬剤師がすべき業務と、事務員に任せられる業務を明確に区別します。
【分担例】
薬剤師が行うべき業務: 調剤、監査、服薬指導、疑義照会
事務員に任せられる業務: 処方箋受付、会計、薬袋作成、一般的な電話対応
定期的なミーティングで業務分担を確認し、負担の偏りを是正します。
対策4:残業時間の可視化と削減目標の設定
残業時間を記録し、可視化することで問題意識が高まります。職場全体で「残業削減」を目標に掲げ、具体的な数値目標を設定しましょう。
【実践方法】
毎日の退勤時間を記録
週・月単位での残業時間を集計
管理者と共有し、改善策を協議
「ノー残業デー」の設定
対策5:適切な休息とストレス管理
激務の中でも、意識的に休息を取ることが重要です。
【休息のポイント】
昼休みは必ず取る: 短時間でも離席してリフレッシュ
有給休暇の計画的取得: 事前に申請し、連休を確保
休日は仕事から離れる: 趣味や運動でストレス発散
睡眠時間の確保: 最低7時間の睡眠を目指す
対策6:上司や経営者への相談と改善提案
激務の状況を一人で抱え込まず、上司や経営者に相談することが重要です。
【相談のポイント】
具体的なデータを示す(残業時間、処方箋枚数)
健康への影響を伝える
改善策を提案する(人員増加、業務効率化、システム導入)
複数人で相談する(一人より説得力が増す)
対策7:働き方の選択肢を広げる
正社員フルタイムにこだわらず、柔軟な働き方を検討します。
【選択肢】
時短勤務: 勤務時間を短縮
パート勤務: 週3〜4日勤務
派遣薬剤師: 勤務日数や時間を調整可能
複数職場での掛け持ち: 一つの職場での負担を軽減
激務の職場を見極めるポイント【転職時の確認事項】
転職を検討する際、事前に激務かどうかを見極めることが重要です。面接時や職場見学で確認すべきポイントを解説します。
求人票での確認ポイント
【チェック項目】
年間休日数: 120日以上が理想
月平均残業時間: 10時間以内が目安
処方箋枚数: 1日の処方箋枚数と薬剤師数のバランス
薬剤師数: 複数名配置されているか
休暇制度: 有給休暇取得率、育児・介護休暇
面接時に確認すべき質問
【質問例】
「平均的な残業時間はどのくらいですか?」
「有給休暇の平均取得日数を教えてください」
「一日の処方箋枚数と薬剤師の配置人数は?」
「業務の繁忙期はいつですか?」
「最近の離職者の退職理由は何でしたか?」
職場見学でのチェックポイント
【観察項目】
スタッフの表情: 笑顔があるか、余裕があるか
職場の雰囲気: ピリピリしていないか
整理整頓: 職場が整っているか
閉局時間: 閉局後の残業状況
休憩の取り方: 昼休みがきちんと取れているか
よくある質問(FAQ)
- Q薬剤師の激務は他の職種と比べてどの程度ですか?
- A医療従事者全体で見ると、医師や看護師ほどではありませんが、責任の重さと業務量の多さから、激務と感じる薬剤師は多くいます。特に処方箋が集中する時間帯や、人員不足の職場では、他の職種と比べても激務の度合いは高いと言えます。
- Q残業代はきちんと支払われますか?
- A法律上、残業代の支払いは義務です。多くの職場では適切に支払われていますが、一部では「みなし残業」として固定残業代が給与に含まれているケースや、サービス残業が常態化しているケースもあります。雇用契約書で残業代の扱いを必ず確認しましょう。
- Q激務を理由に退職するのは甘えでしょうか?
- Aいいえ、甘えではありません。過度な激務は心身の健康を害し、医療ミスのリスクも高めます。自分の健康と患者の安全を守るために、働き方を見直すことは正当な選択です。我慢し続けることが必ずしも正しいとは限りません。
- Q病院と薬局、どちらが激務ですか?
- A一概には言えませんが、病院は夜勤があり生活リズムが乱れやすい一方、薬局は処方箋が集中する時間帯の激務が特徴です。どちらも人員配置や業務体制によって激務の度合いは大きく異なるため、個別の職場環境を確認することが重要です。
- Q激務の職場から転職する際、面接でどう説明すればいいですか?
- A「前職の激務が辛かった」というネガティブな表現は避け、「ワークライフバランスを重視し、長く働ける環境を求めている」「心身の健康を保ちながら、患者さんに質の高いサービスを提供したい」など、前向きな理由に転換して説明しましょう。
まとめ
薬剤師の激務は、業務量の増加、人員不足、多様な業務の並行処理など、構造的な要因によって生じています。激務は心身の健康に深刻な影響を与えるため、早期の対処が重要です。
業務の優先順位付け、効率化、適切な休息など、個人でできる対策を実践しつつ、それでも改善しない場合は転職も検討しましょう。
ワークライフバランスの取れた職場で働くことは、長期的なキャリア満足度と患者への質の高いサービス提供につながります。
まずはキャリアの可能性を知る相談から
キャリア相談・面談依頼はこちらから
田井 靖人
2013年摂南大学法学部を卒業後、不動産業界で土地活用事業に従事。
2019年から医療人材業界へ転身し、薬剤師と医療機関双方に寄り添う採用支援に携わる。
現在は薬剤師が“自分らしく働ける環境”を広げるべく、現場のリアルやキャリアのヒントを発信。 座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。どんな経験も糧に変え、薬剤師の未来を支える言葉を届けている。