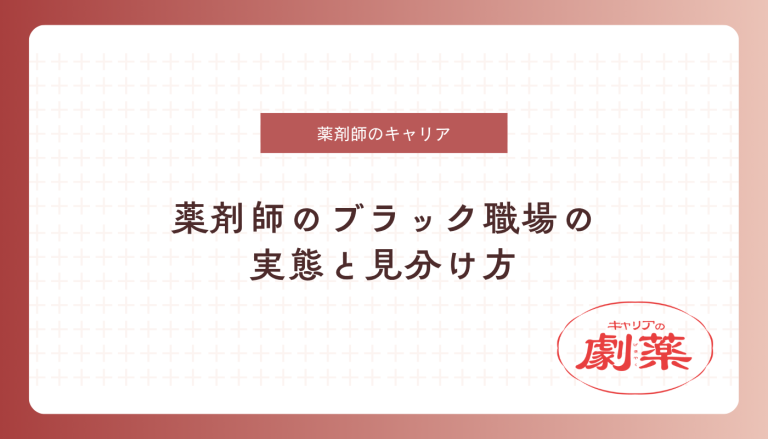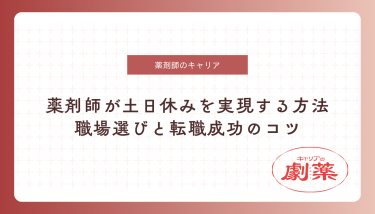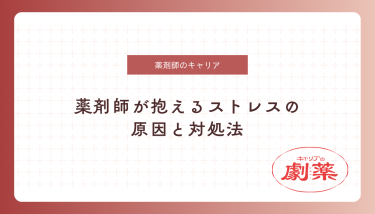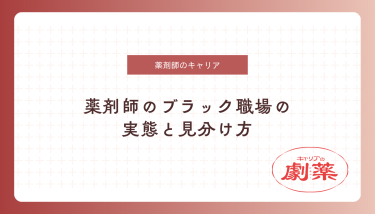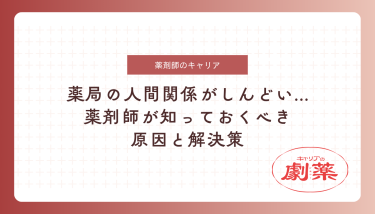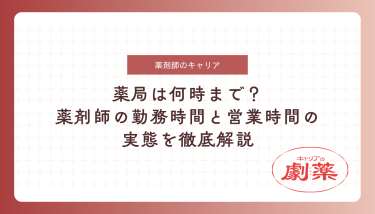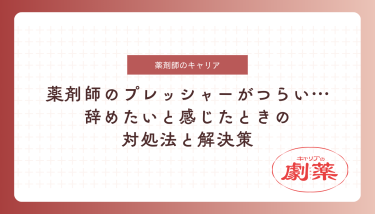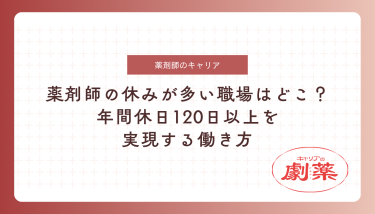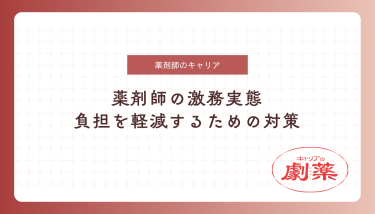薬剤師として働く中で「もしかしてこの職場、ブラックかも?」と感じたことはありませんか。本記事では、実際の調査データに基づいたブラック薬局の実態と、転職で失敗しないための具体的な見分け方を詳しく解説します。
薬剤師のブラック職場とは?定義と実態
ブラック職場という言葉は広く使われていますが、薬剤師業界において具体的にどのような状態を指すのでしょうか。ここでは、法律的な観点と実際の現場の声から、ブラック職場の定義と実態を明らかにします。
ブラック職場の法律的定義
労働基準法では、労働時間や休日、賃金に関する明確な基準が定められています。これらの基準に違反している職場は、法律的にもブラック職場と言えます。
労働基準法における主な規定
労働時間は原則として1日8時間、1週間40時間までと定められており、これを「法定労働時間」と言います。これを超えて労働させる場合は、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要です。
休日については、少なくとも毎週1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。
残業代は、法定労働時間を超えた労働に対して、通常賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。深夜労働(午後10時から午前5時まで)の場合は、さらに25%以上の割増が必要です。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。
薬剤師の残業時間の実態
厚生労働省の統計データによると、薬剤師の残業時間は他の医療職と比較してどのような状況にあるのでしょうか。
薬剤師の平均残業時間
令和4年賃金構造基本統計調査によると、薬剤師の1ヶ月あたりの超過実労働時間(残業時間)は平均9〜10時間です。令和元年の調査では平均11時間、令和3年では平均10時間と報告されており、若干の減少傾向が見られます。
しかし、この数字はあくまで全体の平均であり、従業員1,000人以上の企業では平均残業時間が12〜14時間程度に増加する傾向にあります。また、管理薬剤師や薬局長などの管理職は、スタッフ管理や数値管理、他部署との打ち合わせなど一般薬剤師以外の業務も担当するため、残業時間がさらに多くなる傾向があります。
冬場のインフルエンザ流行期や春の花粉症シーズンなどの繁忙期には、数十時間単位の残業を求められる職場もあり、職場環境によって大きな差があることが分かります。
出典:厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」「令和元年賃金構造基本統計調査」
ブラック薬局に共通する7つの特徴
ブラック薬局には共通する特徴があります。これらの特徴を知っておくことで、就職・転職時に事前に回避できる可能性が高まります。ここでは、実際の調査データと現場の声に基づいた7つの特徴を詳しく解説します。
残業代が支払われない
ブラック薬局の最も代表的な特徴が、残業代の未払いです。
残業代未払いの具体的なパターン
タイムカードや勤怠管理システムが導入されていない職場では、労働時間の記録があいまいになり、残業をしても正確に記録されないケースがあります。
開店前の準備時間や閉店後の片付け時間が勤務時間に含まれず、実質的にサービス残業となっている職場も少なくありません。例えば、9時開店の薬局で8時30分から準備を始めても、9時からの勤務として扱われるケースです。
会社主催の勉強会や研修が就業時間外に開催され、参加が実質的に強制であるにもかかわらず、勤務時間としてカウントされない場合もあります。
一人薬剤師の職場では、休憩時間中も処方箋が持ち込まれれば対応する必要があり、実質的に休憩が取れていないにもかかわらず、休憩時間として扱われているケースもあります。
法律上の問題点
労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させた場合、通常賃金の25%以上の割増賃金を支払う義務があります。残業代の未払いは明確な労働基準法違反です。
また、管理薬剤師であっても、法律上の「管理監督者」に該当しない場合は残業代の支払い義務があります。管理監督者として認められるためには、経営に関する重要な決定に関与していることや、出退勤時間が自由であること、地位にふさわしい待遇を受けていることなど、厳格な条件があります。
休日・有給休暇が取得できない
休日や有給休暇が十分に取得できないことも、ブラック薬局の大きな特徴です。
休日取得の問題
労働基準法では、週1日または4週間で4日以上の休日を与えることが義務付けられていますが、人手不足を理由に休日出勤を強要される職場があります。
シフト制の職場で、希望休が全く通らない、または通りにくい環境は、実質的にブラックな職場環境と言えます。
有給休暇取得の問題
「周りのみんなが取らないから」という理由で有給休暇の取得を断られる、または取得しにくい雰囲気がある職場は要注意です。
2019年4月の働き方改革関連法の施行により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日の有給休暇を取得させることが企業の義務となっています。これを守っていない職場は法令違反です。
長時間労働が常態化している
人手不足による長時間労働や激務も、ブラック薬局の典型的な特徴です。
一人薬剤師の問題
薬剤師が1人しかいない職場では、責任の重い調剤作業を1人で行う必要があり、休憩を取ることが困難です。薬剤師法では、1日に処理する処方箋が41枚を超える場合は、もう1人薬剤師を雇用する必要がありますが、これを守らず過重労働をさせている職場は法令違反です。
休憩が取れない職場環境
調剤室から抜けられない、昼休憩をまともに取れない、常に立ちっぱなしで水分補給する時間もないという状況は、明らかに異常な労働環境です。
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが義務付けられています。休憩時間を取得できない職場は法令違反です。
定時で帰れない雰囲気
雇用契約書には18時終業と記載されているにもかかわらず、実際には19時、20時まで働くことが当たり前になっている職場は要注意です。定時で帰ろうとすると嫌な顔をされる、または明示的に引き留められる環境は、ブラックな職場の特徴です。
人間関係が悪い・パワハラがある
小規模な薬局では特に、人間関係のトラブルが深刻化しやすい傾向があります。
閉鎖的な環境による人間関係の問題
調剤薬局の多くは従業員数10人以下の小規模な職場です。閉鎖的な環境では、一度人間関係が悪化すると改善が難しく、いじめやパワハラが常態化するリスクがあります。
高圧的な薬剤師や調剤薬局事務員がいる、スタッフ同士がギスギスしている、新人に対する指導が厳しすぎるという声は多く聞かれます。
パワハラの具体例
ミスをしたときに他のスタッフの前で大声で叱責される、人格を否定するような発言をされる、無視される、業務に必要な情報を意図的に共有されないなどのパワハラ行為が見られる職場は、明確にブラックです。
厚生労働省では、職場におけるパワーハラスメント防止のための指針を定めており、企業には防止措置を講じる義務があります。
教育制度・研修制度が整っていない
新人や転職者に対する教育体制が整っていない職場も、ブラック薬局の特徴の一つです。
教育制度不備の問題点
十分な研修を行わずに実務に就かせる、分からないことを質問しても「自分で調べて」と突き放される、新人教育を担当する先輩がいないなどの状況は、従業員を育てる意識が低い証拠です。
研修補助費を出したがらない、研修に行く時間があれば実務をこなして欲しいという考えが浸透している職場では、薬剤師としての成長が見込めません。
教育制度不備がもたらす悪影響
基本的なことを教わらないまま現場に出されるため、ミスを連発してしまう、周りに相談できる人がいないため職場で孤立してしまう、スキルアップができず、将来のキャリアに不安を感じるなどの問題が生じます。
大手病院やドラッグストアでは社員教育の一環として教育制度を整えている場所が多い一方、中小薬局では教育制度が不十分なケースが目立ちます。
離職率が高い
頻繁に薬剤師が入れ替わり、長く働いている人が少ない職場は、ブラック薬局である可能性が高いと言えます。
高い離職率の背景
働きにくい職場、仕事が忙しすぎる職場、人間関係が複雑な職場では、薬剤師が定着しないため離職率が高くなります。業務量が多いにもかかわらず給与が低い、福利厚生が充実していないなど待遇面が悪い場合も、薬剤師が離職しやすい傾向にあります。
一般的に、3年以内の離職率が3割を超えている職場は注意が必要です。高い離職率は、労働条件や人間関係が悪いことが原因である可能性が高いためです。
離職率が高い職場の見分け方
常に求人が出ている、面接時に「スタッフの平均勤続年数」を質問すると答えられない、または明らかに短い、職場見学時にベテランスタッフが少ないといった点に注目しましょう。
法令違反・不正請求をしている
最も深刻なブラック薬局の特徴が、法令違反や調剤報酬の不正請求です。
法令違反の具体例
調剤しかしていないのに在宅管理料を算定している、加算算定に該当する指導を行っていないのに不当に加算を算定している、水剤や散剤も含めて調剤すべてを事務スタッフがやっており、監査も事務スタッフが行うことが多く、薬剤師は投薬するだけという状況は、明確な法令違反です。
薬剤師法では、薬剤師でない者が調剤や監査を行うことは禁止されています。これを黙認または強要している職場は、極めて危険なブラック職場です。
不正請求のリスク
不正請求に加担させられた場合、薬剤師個人も責任を問われる可能性があります。スタッフに加算を強要し、意見できないような雰囲気ができあがっている職場は、非常に危険な状態です。
法令違反がある職場で働いている場合は、できるだけ早く転職を検討すべきです。不正に加担していると見なされた場合、薬剤師免許の取り消しや業務停止などの行政処分を受けるリスクもあります。
ブラック職場で働き続けるリスクと影響
ブラックな職場で働き続けることは、薬剤師自身にさまざまな悪影響を及ぼします。ここでは、具体的なリスクと影響について解説します。
身体的・精神的健康への影響
長時間労働や休憩不足、過度なストレスは、薬剤師の健康に深刻な影響を与えます。
慢性的な睡眠不足による免疫力の低下、長時間の立ち仕事による腰痛や足のむくみ、不規則な食事による胃腸障害、過労による体調不良や病気の発症リスクの増加などが挙げられます。
過度なストレスによる不安障害やうつ病の発症リスク、人間関係の悩みによる精神的苦痛、仕事とプライベートのバランスが崩れることによる生活の質の低下、燃え尽き症候群(バーンアウト)による意欲の喪失などが懸念されます。
ストレスがキャパシティを超えると、周りからのプレッシャーがきつく感じられ、精神的に参ってしまうことがあります。自分が壊れてしまう前に、適切な対処が必要です。
調剤過誤のリスク増加
ブラックな職場環境は、調剤過誤のリスクを高める要因となります。
長時間労働による集中力の低下、休憩不足による疲労の蓄積、人手不足による確認体制の不備、業務に追われて監査が不十分になる、精神的ストレスによる判断力の低下などが、調剤過誤のリスクを高めます。
調剤過誤は患者様の健康や生命に関わる重大な問題であり、薬剤師としての責任を全うできない環境で働き続けることは、患者様の利益にもなりません。
スキルアップの機会損失
ブラックな職場では、薬剤師としての成長機会が失われます。
研修や勉強会に参加する時間や機会がない、新しい医薬品知識を学ぶ余裕がない、専門資格取得のための学習時間が確保できない、先輩薬剤師から適切な指導を受けられないなどの問題があります。
薬剤師としてのキャリアを考えた場合、スキルアップの機会が失われることは、将来の選択肢を狭めることにつながります。
キャリアへの悪影響
ブラックな職場で働き続けることは、長期的なキャリアにも悪影響を及ぼします。
心身の健康を損なうことで、長期的に薬剤師として働き続けることが困難になる可能性があります。スキルアップの機会が失われ、市場価値が上がらないリスクもあります。
また、ブラックな職場で短期間で離職を繰り返すと、次の転職活動で不利になる可能性があります。適切なタイミングで転職を決断することが重要です。
ブラック職場を見分けるチェックポイント
転職前にブラック職場を見分けることは、失敗を防ぐために非常に重要です。ここでは、具体的なチェックポイントを10個紹介します。
求人情報の確認事項
求人情報には、ブラック職場を見分けるヒントが隠されています。
注意すべき求人の特徴
常に求人が出ている職場は、離職率が高い可能性があります。「やる気のある方」「体力に自信のある方」など抽象的な表現が多く、具体的な業務内容や労働条件の記載が少ない求人は要注意です。
給与が相場より明らかに高い場合は、その理由を確認する必要があります。高給与の代わりに労働条件が厳しい可能性があります。
「アットホームな職場」という表現が多用されている場合は、実際には人間関係に問題がある可能性も考えられます。
確認すべき具体的な項目
雇用形態(正社員、契約社員、パートなど)、勤務時間(始業・終業時刻、休憩時間)、休日・休暇(年間休日数、有給取得率)、給与(基本給、各種手当の内訳、賞与の有無)、残業時間(月平均残業時間の記載があるか)、福利厚生(社会保険、研修制度、資格取得支援など)を必ず確認しましょう。
面接時の質問事項
面接は、職場の実態を知る重要な機会です。以下の質問を必ず行いましょう。
労働環境に関する質問
1日の処方箋枚数と薬剤師の配置人数はどのくらいですか、残業時間は月平均どのくらいですか、残業代は全額支給されますか、有給休暇の取得率はどのくらいですか、スタッフの平均勤続年数はどのくらいですか、離職率はどのくらいですか、繁忙期はいつで、どのくらい忙しくなりますかなどを質問しましょう。
教育・研修に関する質問
新人研修の内容と期間を教えてください、先輩薬剤師による指導体制はありますか、外部研修への参加は可能ですか、研修費用の補助制度はありますか、認定薬剤師資格取得の支援制度はありますかなども確認が必要です。
これらの質問に対して、明確に答えられない、または答えを濁す場合は、注意が必要です。
職場見学での確認事項
可能であれば、必ず職場見学を申し出ましょう。実際の職場を見ることで、求人情報や面接だけでは分からない実態が見えてきます。
職場見学で観察すべきポイント
スタッフの表情や雰囲気を観察しましょう。疲れた表情、ピリピリした雰囲気、スタッフ同士のコミュニケーションが少ないなどは要注意サインです。
調剤室の広さと設備を確認します。狭すぎる、設備が古い、整理整頓されていないなどは、働きにくい環境の可能性があります。
薬剤師の動きと業務量を観察しましょう。常にバタバタしている、休憩を取っている様子がない、患者様が大勢待っているなどは、人手不足の可能性があります。
スタッフの年齢構成も確認ポイントです。若手ばかりでベテランがいない場合は、離職率が高い可能性があります。
転職エージェントの活用
転職エージェントは、職場の内部情報を持っていることが多く、ブラック職場を避けるために非常に有効です。
転職エージェントが提供できる情報
実際の残業時間や有給取得率、職場の雰囲気や人間関係、離職率や離職理由、過去の転職者からのフィードバック、給与交渉の余地などの情報を提供してくれます。
経験豊富なキャリアアドバイザーは、求人票に書かれていない情報を把握しており、ブラック職場を事前に除外してくれることもあります。
口コミサイトの活用
インターネット上の口コミサイトも、職場選びの参考になります。
口コミサイトで確認すべきポイント
給与水準や福利厚生の実態、有給消化率や残業時間の実態、職場の雰囲気や人間関係、教育制度や研修の充実度、ワークライフバランスの実現度などを確認しましょう。
ただし、口コミは個人の主観的な意見であり、すべてが正確とは限りません。複数の口コミを総合的に判断し、一つの参考情報として活用することが重要です。
労働条件通知書・雇用契約書の確認
内定後は、必ず労働条件通知書や雇用契約書の内容を詳細に確認しましょう。
確認すべき項目
雇用形態と雇用期間、勤務場所、始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇、賃金(基本給、各種手当、賞与、昇給)、残業に関する取り決め、退職に関する事項などを必ず確認します。
面接時に聞いた内容と、契約書の内容に相違がないかを必ず確認しましょう。相違がある場合は、必ず質問し、納得してから契約することが重要です。
SNSや掲示板の情報
SNSや掲示板での評判も参考になりますが、情報の真偽を見極める必要があります。
SNS・掲示板の活用方法
薬剤師向けの掲示板やSNSグループで、その職場の評判を調べてみましょう。ネガティブな情報が多い場合は要注意です。
ただし、匿名の情報は信憑性に欠ける場合もあるため、あくまで参考程度にとどめ、最終的には自分の目で確かめることが大切です。
試用期間の活用
多くの職場では、入社後に試用期間が設けられています。この期間を活用して、職場の実態を見極めましょう。
試用期間中に確認すべきこと
実際の残業時間や業務量、教育・指導体制の実態、職場の人間関係、有給休暇の取得しやすさ、求人情報や面接で聞いた内容との相違などを確認します。
試用期間中に「この職場はブラックだ」と確信した場合は、早めに退職を検討することも選択肢の一つです。長く働けない職場で我慢し続けるより、早めに次のステップに進む方が、キャリア上有利になることもあります。
薬剤師仲間からの情報収集
薬剤師の同僚や知人から、職場の情報を収集することも有効です。
情報収集の方法
薬学部の同級生や先輩・後輩から情報を集める、薬剤師会などの勉強会で知り合った薬剤師から話を聞く、転職経験のある薬剤師から体験談を聞くなどの方法があります。
実際に働いている人からの生の声は、非常に参考になります。
自分の優先順位を明確にする
最後に、自分が職場に何を求めるのか、優先順位を明確にしておくことが重要です。
優先順位の例
ワークライフバランスを重視するか、高収入を重視するか、スキルアップの機会を重視するか、人間関係の良さを重視するか、通勤時間の短さを重視するかなど、人によって優先する条件は異なります。
すべての条件が完璧に揃った職場はほとんどありません。自分にとって絶対に譲れない条件と、妥協できる条件を明確にしておくことで、自分に合った職場を見つけやすくなります。
今すぐできるブラック職場への対処法
現在ブラックな職場で働いている薬剤師のために、具体的な対処法を紹介します。
上司や人事部に相談する
まずは、職場内での改善を試みることが重要です。
具体的な問題点を整理し、事実に基づいて説明する、改善してほしい点を明確に伝える、感情的にならず、冷静に話すことを心がけましょう。
残業代の未払いや労働時間の問題など、明確な法令違反がある場合は、労働基準法に基づいて改善を求めることができます。
労働基準監督署への相談
職場内での改善が見込めない場合は、外部機関への相談を検討しましょう。
労働基準監督署では、労働基準法違反(残業代の未払い、違法な長時間労働など)に関する相談・指導、労働条件や労働時間に関するアドバイス、必要に応じて職場への立ち入り調査などを行います。
相談は無料で、匿名でも可能です。証拠(タイムカード、給与明細、雇用契約書など)があると、相談がスムーズに進みます。
弁護士への相談
残業代の請求や不当解雇など、法的な問題が絡む場合は、弁護士への相談が有効です。
未払い残業代の請求をしたい、不当解雇や退職強要を受けた、パワハラやセクハラの被害を受けた、労働条件の不利益変更を強要されたなどの場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
初回相談無料の法律事務所も多くあります。また、日本弁護士連合会の法律相談センターでは、30分5,000円程度で相談できます。
転職を決断する
職場の改善が見込めず、心身の健康に悪影響が出ている場合は、転職を決断することも重要な選択肢です。
心身の健康に明らかな悪影響が出ている、職場の改善を試みたが変化がない、法令違反が常態化しており改善の見込みがない、キャリアアップの機会が全くないなどの場合は、早めの転職を検討しましょう。
薬剤師は転職しやすい職種であり、実際に薬剤師の7〜8割が一度は転職を経験しています。ブラックな職場で我慢し続けるより、より良い環境を求めて転職することは、決して逃げではありません。
心身のケアを最優先にする
どのような対処法を選ぶにせよ、自分の心身の健康を最優先に考えることが重要です。
十分な睡眠と休息を取る、趣味やリフレッシュの時間を確保する、信頼できる人に相談する、必要に応じて医療機関(心療内科など)を受診するなどを心がけましょう。
職場には従業員支援プログラムやメンター制度がある場合もあります。これらのプログラムや制度を上手に活用することで、専門家の支援を受けることができます。
ストレスがキャパシティを超えそうなときは、「頑張りすぎない精神」を持って、薬剤師の仕事と向き合うようにしましょう。自分自身のキャパシティを知り、壊れるまで無理をしないことが大切です。
まとめ
ブラック職場には、残業代未払い、休日取得困難、長時間労働、人間関係の悪化、教育制度不備、高い離職率、法令違反という7つの共通特徴があります。
職場選びでは求人情報の精査、面接での質問、職場見学、転職エージェントの活用が重要であり、現在ブラック職場で働いている場合は、上司への相談、外部機関への相談、転職の検討など、状況に応じた適切な対処が必要です。
自分の心身の健康を最優先に考え、無理をせず、より良い職場環境を求めることは決して逃げではありません。理想的な職場環境で薬剤師としてのキャリアを築いていきましょう。
まずはキャリアの可能性を知る相談から
キャリア相談・面談依頼はこちらから
田井 靖人
2013年摂南大学法学部を卒業後、不動産業界で土地活用事業に従事。
2019年から医療人材業界へ転身し、薬剤師と医療機関双方に寄り添う採用支援に携わる。
現在は薬剤師が“自分らしく働ける環境”を広げるべく、現場のリアルやキャリアのヒントを発信。 座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。どんな経験も糧に変え、薬剤師の未来を支える言葉を届けている。