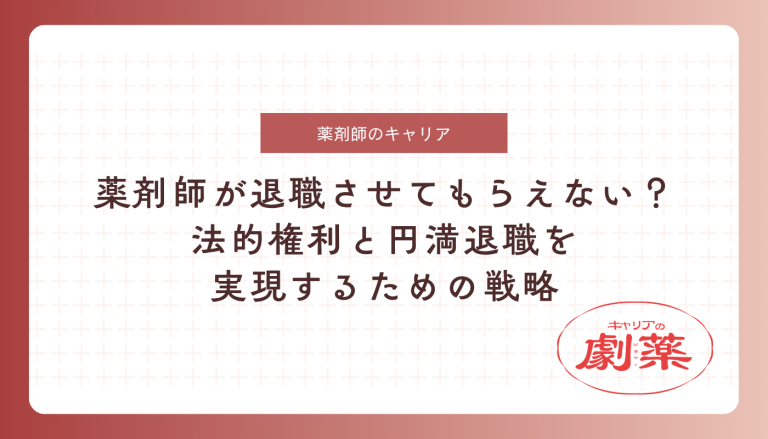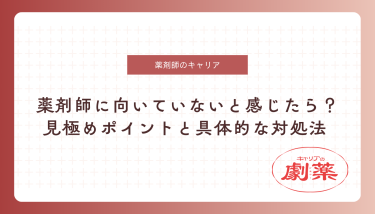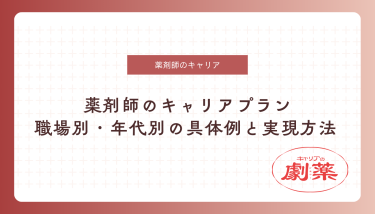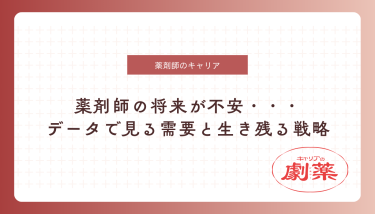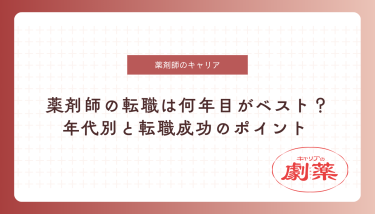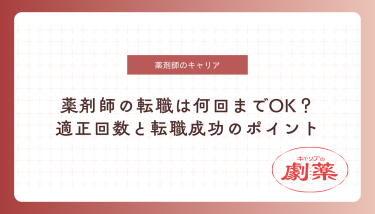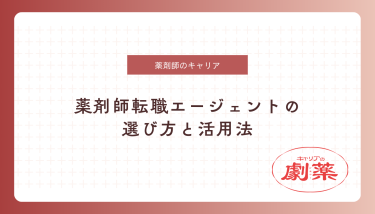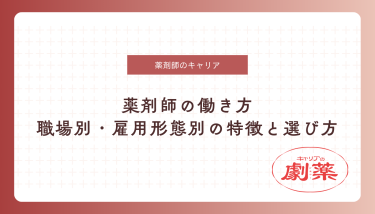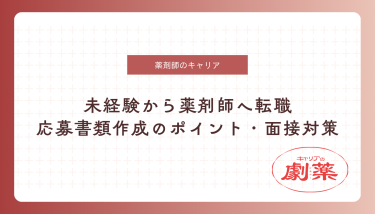「退職を申し出たのに引き止められて辞められない」「後任が決まるまで待ってほしいと言われ続けている」。薬剤師業界では人手不足を背景に、退職時の引き止めに悩む方が少なくありません。
しかし、法律上は労働者に退職の自由が保障されています。
本記事では、退職させてもらえない状況への対処法、法的根拠、そして円満退職を実現するための具体的な手順を解説します。
薬剤師が退職を引き止められる背景と実態
薬剤師が退職を申し出た際に強く引き止められるケースは珍しくありません。まず、薬剤師業界における退職の実態と引き止めが起こる背景を見ていきましょう。
薬剤師業界の離職率と人手不足の現状
厚生労働省が公表している産業別の離職率によると、薬剤師を含む「医療、福祉」業界における離職率は14.2%となっています。これは全産業の平均離職率15.0%と比較しても平均的な数値です。
一方で、令和2年度の厚生労働省の調査によると、医療・福祉業界の離職率は14.2%でした。実際には「辞めたい」と思いながらも引き止められて辞められないでいる薬剤師も存在すると考えられます。
出典:厚生労働省「令和2年雇用動向調査 産業別の入職と離職」
なぜ薬剤師は引き止められやすいのか
薬剤師が退職を引き止められる主な理由は以下の通りです。
人材紹介費用の負担
薬剤師の採用には、人材紹介会社経由で100万円を超える費用が発生することもあります。経営者や管理職は、できる限り既存の薬剤師に残ってもらいたいと考えています。
後任者の確保の難しさ
薬剤師は慢性的な人手不足であり、特に地方や小規模薬局では後任者を見つけることが容易ではありません。そのため「後任が決まるまで待ってほしい」という引き止めが頻繁に発生します。
引き継ぎ期間の確保
処方箋の長期化により60日処方や90日処方があり、担当患者への対応や他スタッフへの引き継ぎに時間がかかることを理由に、退職日を先延ばしにされることがあります。
退職は労働者の権利|法的根拠を正しく理解する
退職させてもらえない状況に直面した際、最も重要なのは法的な権利を正しく理解することです。ここでは、退職に関する法律の規定を詳しく解説します。
民法627条|2週間前の申し出で退職可能
期間の定めのない労働契約(正社員など)の場合、民法第627条第1項により、労働者はいつでも退職の申し出をすることができ、申し出から2週間を経過すると労働契約が終了します。この際、会社の同意は必要ありません。
民法第627条第1項 「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
出典:民法第627条
この規定は、使用者による不当な人身拘束を防ぐ趣旨のものであり、労働者の退職の自由を保障する重要な法律です。
就業規則より民法が優先される
多くの調剤薬局や病院の就業規則には「退職は2か月前(管理薬剤師は3~6か月前)に上長に申告すること」と決められているケースがあります。しかし、法律上、これらの規定よりも民法627条が優先されます。
厚生労働省のウェブサイトでも、2週間を超える解約予告期間の設定は無効とされるというのが裁判例の基本的な方向性とされています。
就業規則はあくまでも「会社のルール」であり、法的拘束力は民法に劣ります。したがって、就業規則で「退職1ヶ月前申告が必要」と記載があったとしても、退職2週間前に申告していれば法的には問題ありません。
退職届と退職願の違い
退職の意思表示には「退職届」と「退職願」がありますが、法的な意味が異なります。
退職届:使用者の承諾は不要で、提出から2週間が経過すると雇用関係が終了します。
退職願:退職に使用者の承諾が必要と解釈される可能性があります。
強い意思で退職を伝える場合は「退職届」を使用することをおすすめします。内容証明郵便などを利用し、退職の意思表示をしたことを明確にしておくことも有用です。
出典:連合「よくある労働相談Q&Aコーナー」
引き止めに遭った時の具体的な対処法
実際に退職を引き止められた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。状況別の対処法を解説します。
その場で退職届を提出する
退職を申し出ると、多くのケースで管理職と面談の機会を設けることになります。ほとんどの方がその場で引き止めに遭います。
最も効果的な方法は、その場で退職届を提出することです。退職届を提出すれば、それ以上引き止められることはほとんどありません。逆にその場で提出しないと、理由をつけて退職日を引き延ばされる可能性があります。
引き止めを回避できる退職理由の伝え方
引き止めを避けるためには、会社側で対処できない理由を伝えることが重要です。以下のような理由が効果的です。
引き止めにくい退職理由:
家族の介護が必要になった
配偶者の転勤に伴い引っ越しをする
健康上の問題で勤務継続が難しい
新しい分野にチャレンジしたい(具体的なキャリアプラン)
すでに次の職場の入社日が決まっている
避けるべき退職理由:
給与が低い→「給与を上げる」と提案される
残業が多い→「残業を減らす」と提案される
人間関係が合わない→「異動させる」と提案される
あいまいな理由を伝えたり、どっちつかずの態度をとると、引き止めが長引く可能性があります。退職理由を明確に伝え、退職は考え抜いた末に決めた結論だという強い意思表示をすることが重要です。
条件改善の提案には慎重に対応する
給与アップや待遇改善、異動などの提案をされた場合でも、焦らずに冷静に対応しましょう。
引き止めの際の提案は「口約束」であることが多く、必ずしも提示された改善案が実現するとは限りません。
一度退職を申し出た事実は消えず、「またすぐに辞めると言い出すのでは?」と同僚に思われる可能性があります。
残念ながら、退職を取り消したところで不満が改善されるケースはほぼありません。
条件改善の提案があっても、「ありがたいお話ですが、すでに退職を決意しています」「条件が変わっても、環境を変えたい気持ちは変わりません」と明確に断ることが重要です。
円満退職を実現するための実践ステップ
法的には2週間前の申し出で退職できますが、円満退職を目指すなら適切なステップを踏むことが大切です。
退職を伝えるタイミング
推奨タイミング
・理想は退職希望日の1.5~2ヶ月前
・最低でも1ヶ月前には申し出る
・繁忙期は避ける
・就業規則の規定も可能な限り考慮する
直前すぎると悪い印象を持たれることが多いため、通常1か月前に申し出れば間違いありません。ただし、「引き止められるから」といって職場の都合ばかりを優先する必要はなく、自分の希望も伝え、適切なタイミングで退職できるように交渉しましょう。
退職を伝える相手と手順
1. 直属の上司に声をかけ、時間を取ってもらう 「ご相談があるのですが」「少しお時間をいただけないでしょうか」と前置きして上司に時間を取ってもらいます。伝える際には、ほかのスタッフがいる職場ではなく、バックヤードや休憩室など落ち着いた空間を選びましょう。
2. 退職の意思を、退職日と合わせて伝える 明確な退職日を示さないと、「引き止めれば残ってくれるだろう」と思われ、退職をうやむやにされてしまう可能性があります。しっかりと上司の目を見て、「この日に退職したい」旨を伝えてください。
3. 退職理由を説明する 準備した退職理由を誠実に伝えます。職場への感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。
注意点: 会社は組織ですので、伝える相手を間違えると退職交渉が難航します。必ず直属の上司から伝えるようにしてください。
引き継ぎを丁寧に行う
円満退職のためには、後任者への引き継ぎを丁寧に行うことが不可欠です。
具体的な引き継ぎ内容
担当している患者の服薬指導のポイントを伝える
薬歴管理の方法や注意すべき点を説明する
取引業者や発注業務の手順を整理する
トラブル対応の事例や対応マニュアルを共有する
業務の流れや注意点をまとめた資料を作成する
しっかりと引き継ぎを行うことで、退職後も職場に迷惑をかけず、円満に辞めることができます。
必要な書類の準備と受領
職場から返却してもらう書類
・薬剤師免許証
・保険薬剤師登録票
・年金手帳
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
・離職票(転職先が決まっていない場合)
職場に返却する物
・健康保険証
・社員証
・業務で使用していた物品
離職票は失業保険を受給するために必要な書類なので、退職後に失業保険の受給を考えている場合は必ず受領しましょう。
それでも退職させてもらえない場合の最終手段
適切な手順を踏んでも退職させてもらえない場合、以下の方法を検討しましょう。
より上位の管理職や人事部に相談する
直属の上司が退職を認めてくれない場合、より階層が上にあたる管理職・経営層や人事部に相談しましょう。法律を根拠として交渉をすれば、退職もスムーズに進むはずです。
労働基準監督署への相談
正当な退職手続きを行ったにもかかわらず退職させてもらえない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働関連法令に違反する事業者に対して指導や是正勧告を行う権限を持っています。
退職代行サービスの活用
退職を言い出しづらい、引き止めに遭っている、心身に不調をきたしているといった状況の場合は、退職代行サービスの利用も選択肢の一つです。
退職代行のメリット
・上司や同僚と顔を合わせずに辞められる
・自分で言いにくいことを言うストレスがない
・即日対応している業者なら、すぐに出社の必要がなくなる
薬剤師のように激務やストレスにさらされやすい職場では、自力で辞めるのが難しいケースが少なくありません。もし辞める際にトラブルになりそうなら、労働組合と提携もしくは弁護士監修のサービスを選ぶと安心です。
有給休暇の消化
退職前に有給休暇を消化できるかどうかも重要なポイントです。法律上、退職時の有給休暇の消化は労働者の権利であり、職場側が拒否することはできません。
労働基準法39条に基づき、労働者は取得日を指定して年次有給休暇を取得する権利があり、使用者は「事業の正常な運営を妨げる場合」以外はその申請を拒めません。退職が決まっている労働者については、退職日以降に振り替えることが不可能なため、実質的に時季変更権は行使できないと解されています。
薬剤師業界の特性を踏まえた退職のポイント
薬剤師業界には独特の特性があり、それを理解した上で退職活動を進めることが重要です。
業界の狭さを意識する
薬剤師業界は広いようで狭い業界です。元同僚の薬剤師と転職先の上司が知り合いだった、という話は決して珍しくありません。以前の職場と良好な関係を保っておくことは、自分のキャリアを守るうえでも非常に重要です。
転職理由に「人間関係への不満」を挙げる薬剤師は少なくありませんが、薬剤師業界は横のつながりが強いため、人間関係のトラブルは避けるべきです。たとえ職場の人間関係に不満をもっていたとしても、上司や同僚と良好な関係を築いていくことは、薬剤師としてキャリアを伸ばしていくうえできっとプラスに働きます。
転職先を決めてから退職を申し出る
次の転職先がまだ決まっていない状況で退職を申し出ると、上司がそれを知れば退職を引き止められ、断りきれなくなってしまう可能性があります。
すでに新しい職場の入社日が決まっていることを伝えれば、「引き止めるのは難しい」と判断されやすくなります。ただし、転職先が決まっていないのに「決まっている」と嘘をつくのは避けたほうがよいでしょう。
退職後のキャリア形成を考える
薬剤師の転職は珍しくありませんが、あまりに短期間での転職を繰り返すと、次の転職時に不利になる可能性があります。
退職を決断する前に、本当に今退職すべきなのか、改善の余地はないのかを冷静に考えることも大切です。
まとめ
薬剤師が退職を引き止められる状況は珍しくありませんが、民法627条により労働者には退職の自由が保障されており、2週間前の申し出で退職することが可能です。引き止めに遭った場合は、その場で退職届を提出し、会社側で対処できない明確な退職理由を伝えることが重要です。
円満退職を目指すなら1.5~2ヶ月前に申し出て丁寧な引き継ぎを行い、それでも退職させてもらえない場合は上位管理職への相談や労働基準監督署、退職代行サービスの活用を検討しましょう。
薬剤師業界の特性を理解し、適切な手順で退職活動を進めることで、次のキャリアへとスムーズに移行できます。
まずはキャリアの可能性を知る相談から
キャリア相談・面談依頼はこちらから
田井 靖人
2013年摂南大学法学部を卒業後、不動産業界で土地活用事業に従事。
2019年から医療人材業界へ転身し、薬剤師と医療機関双方に寄り添う採用支援に携わる。
現在は薬剤師が“自分らしく働ける環境”を広げるべく、現場のリアルやキャリアのヒントを発信。 座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。どんな経験も糧に変え、薬剤師の未来を支える言葉を届けている。