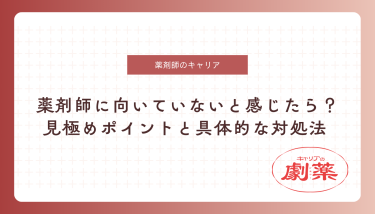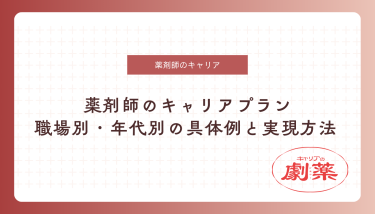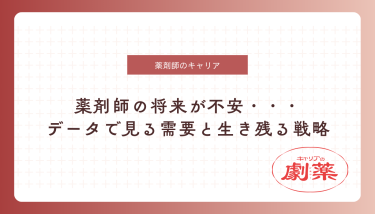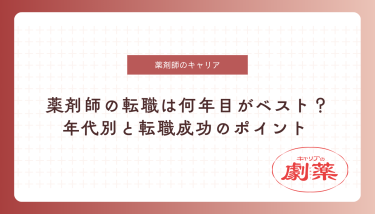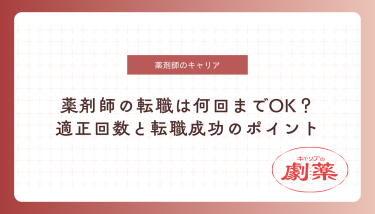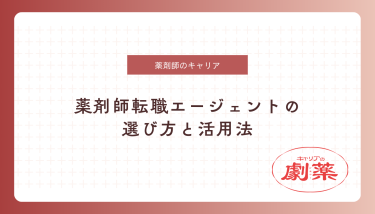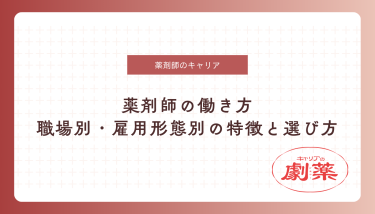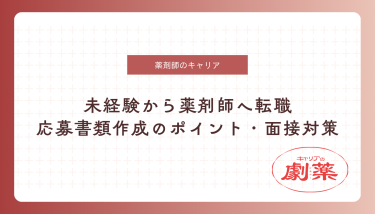薬剤師として転職を考えている方にとって、転職先の離職率は重要な判断材料です。「せっかく転職したのにすぐ辞めることになったら」と不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、最新の統計データをもとに薬剤師の離職率の実態を明らかにし、長く働ける職場を見極めるための具体的なポイントを解説します。
薬剤師の離職率はどのくらい?最新データで見る業界の実態
薬剤師の離職率について、公的機関が発表している最新のデータをもとに詳しく見ていきましょう。
医療・福祉業界全体の離職率
厚生労働省が公表している「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、薬剤師を含む医療・福祉業界における離職率は14.6%でした。これは全産業の平均離職率15.4%と比較すると、わずかに低い水準となっています。医療・福祉業界は専門性の高い業界であり、資格を持つ専門職が多いことから、比較的安定した雇用環境が維持されていると言えます。
出典:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
薬剤師の平均転職回数
エムスリーキャリア株式会社の調査によると、薬剤師の平均転職回数は年齢によって変化し、20~30代で平均1.7回、40代で平均2.8回、50代で平均3.1回、60代で平均3.3回となっています。キャリアが長くなるにつれて転職回数も増える傾向にあり、薬剤師にとって転職は珍しいことではありません。
出典:エムスリーキャリア株式会社「薬剤師の転職動向アンケート」
職場別で見る薬剤師の離職率の違い
薬剤師の働く職場によって、離職率には大きな違いがあります。ここでは主な職場ごとの離職傾向を、信頼できるデータをもとに解説します。
病院薬剤師の離職率
厚生労働省の補助による2019年の調査(1,394病院対象)では、約半数の病院が「薬剤師の離職率は5%未満」と回答しています。さらに、離職率10%未満は全体の約66%に達しており、病院薬剤師の離職率は総じて低い傾向にあります。
病院機能別では、特定機能病院は約8割が離職率10%未満で、全施設が20%未満という結果でした。療養型・精神科病院では約半数が5%未満だが、一部施設では50%超と二極化している側面もあります。
病院薬剤師は専門的な医療知識を深められる環境がある一方、夜勤や当直による身体的負担、時間外の勉強会や研修参加の負担、給与水準が薬局より低い傾向(特に20~30代)、医師・看護師との人間関係のストレスなどの理由で離職を考える薬剤師もいます。
出典:厚生労働省補助事業「病院における薬剤師の働き方の実態を踏まえた生産性の向上と薬剤師業務のあり方に関する研究」
調剤薬局・ドラッグストア・その他の離職傾向
調剤薬局は薬剤師の主要な就業先であり、離職率は比較的低い傾向にあります。勤務時間が決まっていて夜勤が少なく、ワークライフバランスを保ちやすいことが理由です。ただし、業務のルーティン化による成長実感の欠如、キャリアアップの機会の少なさ、契約期間満了(非常勤薬剤師の場合)などの理由で離職が発生することがあります。
ドラッグストアで働く薬剤師の離職率も比較的低いとされています。シフト制で柔軟な働き方ができることや、パート・アルバイトとしての雇用が多いことが特徴です。ただし、企業や店舗によって労働環境は大きく異なり、人手不足による長時間労働、レジ業務や品出しなど調剤以外の業務負担、土日祝日の出勤が多い、深夜営業店舗での夜勤などの要因で離職率が高くなる店舗もあります。
離職率が高い職場の5つの特徴
離職率が高い職場には共通する特徴があります。転職先を選ぶ際は、以下のポイントに注意しましょう。
①給与水準が低い・昇給制度が不透明
給与への不満は離職の主要因となります。単に初年度の年収が低いだけでなく、年次昇給がない、または昇給率が極端に低い(1%未満)、業務量や責任に見合わない給与設定、賞与や各種手当が少ない、残業代が適切に支払われないなどの問題がある職場は離職率が高くなります。
初年度の年収が20万円低くても、昇給率が高ければ5年後には逆転することもあります。長期的なキャリアを考える場合、昇給制度の確認が不可欠です。
②極端な人手不足で業務負担が大きい
人手不足の職場では、1人あたりの業務量が過大になり、離職の連鎖が起こりやすくなります。調剤薬局では、薬剤師1人が1日に応需できる処方箋枚数は基本的に40枚までとされています。常時この上限に近い状態で稼働している薬局は、業務負担が大きいと判断できます。
③勤務時間・休日が不規則または少ない
長時間労働や休日の少なさは、心身の健康を害し離職につながります。年間休日110日未満(業界平均は120日前後)、シフト制で希望休が取りにくい、連休取得が難しい、突発的な休日出勤が頻繁にあるなどの職場は要注意です。
④人間関係が良好でない・職場の雰囲気が悪い
2021年12月~2022年2月に実施された調査では、薬局薬剤師の退職理由として「職場の人間関係」が8.0%を占め、「契約期間の満了」に次いで多い結果となりました。人間関係の問題が起きやすい職場の特徴として、少人数の薬局で人間関係が固定化、管理薬剤師や経営層とのコミュニケーション不足、ハラスメントへの対策が不十分、スタッフ間の業務負担の偏りなどがあります。
⑤キャリアアップ・スキルアップの機会が少ない
成長機会の欠如は、特に意欲的な薬剤師にとって大きな離職要因となります。研修制度やセミナー参加支援がない、専門薬剤師・認定薬剤師の資格取得支援がない、業務内容が単調で新しい学びが得られない、管理職への昇進機会が限られているなどの職場は、離職率が高くなる傾向があります。
薬剤師が離職を考える主な理由
実際に薬剤師が「辞めたい」と考える具体的な理由を、調査データとともに解説します。
①結婚・出産・育児などのライフイベント
病院薬剤師の離職理由で最も多いのが「個人的理由(結婚)」です。一方、薬局薬剤師では14項目中7位という結果でした。この差は、薬局の方が時短勤務や週3日勤務など、ライフステージに合わせた働き方がしやすいことを示しています。
厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」によると、育児休業終了後の復職率は女性が93.2%に達しています。育児サポートが充実している職場ほど、離職率は低くなる傾向にあります。
出典:厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」
②契約期間の満了
薬局薬剤師の離職理由で最も多いのが「契約期間の満了」です。薬局は病院よりも非常勤薬剤師が多く、2018年4月~2021年3月の採用傾向では、病院11.8%に対し薬局は29.8%と約2.5倍です。派遣薬剤師の契約期間は最長3年、契約職員は更新を含めて最長5年間となっており、この期限に伴う離職が多く発生しています。
③職場環境・人間関係への不満
前述の通り、人間関係は離職の大きな要因です。調剤薬局は少人数運営の店舗も多いため、「職場環境への不満」「職場の人間関係」を理由とする退職は、病院(3.2%、4.4%)よりも薬局(4.7%、8.0%)の方が多くなっています。
④給与・待遇への不満
給与に関する不満は、「年次昇給を約束したのに毎年見送られる」「管理職との関係で昇給額が変わる不公平な評価」「業務量に見合わない低賃金」「残業代が適切に支払われない」などの具体的な問題として表れます。
厚生労働省「第24回医療経済実態調査」によると、一般従業員と管理薬剤師の年収差は平均223.7万円、1店舗のみの個人薬局の管理薬剤師は平均905.9万円、100店舗以上のチェーン薬局の管理薬剤師は平均560.9万円となっており、格差は345.0万円にも及びます。店舗規模や役職によって大きな給与格差が存在します。
出典:厚生労働省「第24回医療経済実態調査(医療機関等調査)」
⑤その他の離職理由
その他、業務負担・残業の多さ、転勤・異動への不満、キャリアの不透明性・成長機会の欠如なども離職の要因となります。特に人手不足の職場では、長時間残業、休憩時間が確保できない、有給休暇が取得しにくい、持ち帰り仕事が常態化するなどの問題が発生します。
長く働ける職場を選ぶための5つのチェックポイント
離職率の低い、長く働き続けられる職場を見極めるための具体的なポイントを解説します。
①離職率・定着率を確認する
最も直接的な指標が離職率・定着率です。多くの企業は公表していませんが、上場企業は有価証券報告書で平均勤続年数を公開、転職エージェントに問い合わせる、企業の採用ページやIR情報を確認、口コミサイトで実際の声を確認するなどの方法で確認できます。
目安として、医療・福祉業界の新卒3年以内離職率は38.0%(2019年厚生労働省調査)、理想的な離職率は5~10%以下です。離職率が極端に低い(5%未満)場合も、組織の硬直化などの可能性があるため、理由を確認することをおすすめします。
②給与体系と昇給制度を詳細に確認する
初年度の年収だけでなく、長期的な収入の見通しを確認しましょう。年次昇給の有無と昇給率(最低でも2%以上が望ましい)、賞与の支給実績(年何回、何ヶ月分か)、各種手当(住宅手当、通勤手当、資格手当など)、管理職手当や役職手当の金額、評価制度と昇進の仕組みなどを確認すべきです。給与テーブルや昇給実績を開示している企業は、透明性が高く信頼できる傾向にあります。
③勤務時間・残業・休日体制を確認する
ワークライフバランスを保つために重要なチェックポイントです。年間休日数(120日以上が望ましい)、月間平均残業時間(具体的な数値を確認)、有給休暇の取得率(70%以上が理想)、連休取得の実績、シフトの柔軟性、休日出勤の頻度などを確認しましょう。「残業少なめ」などの曖昧な表現ではなく、具体的な数値を確認することが重要です。
④職場見学を必ず実施する
書面やオンラインでは分からない職場の雰囲気を、実際に確認しましょう。スタッフ同士のコミュニケーションの様子、薬剤師の表情や業務の進め方、調剤室の整理整頓状況、患者さんへの対応の質、業務の分担状況、休憩室の環境などを確認すべきです。可能であれば、実際に働いている薬剤師と話す機会を設けてもらいましょう。
⑤育児・介護サポートの充実度を確認する
長期的なキャリアを考える上で、ライフイベントへのサポートは不可欠です。産休・育休の取得実績と復職率、時短勤務制度(利用可能期間と短縮時間)、育児休業中のフォロー体制、保育施設の有無や保育補助、介護休暇制度、復職後のキャリア支援などを確認しましょう。研修制度が充実している職場は、薬剤師の成長を重視しており、長期的な雇用を前提としている傾向があります。
転職を成功させるための実践ステップ
離職率の低い職場への転職を成功させるための具体的なステップを解説します。
ステップ1
まず、自分が職場に求める条件を整理しましょう。最優先事項(給与、勤務地、勤務時間など)、妥協できる点・できない点、5年後、10年後のキャリアビジョン、ライフプランとの整合性を考えるべきです。優先順位を決めておくことで、求人選びの軸がブレなくなります。
ステップ2
一つの情報源だけに頼らず、多角的に情報を集めましょう。転職エージェント(複数登録を推奨)、企業の公式サイト・採用ページ、口コミサイト、業界ランキングサイト、実際に働いている知人からの情報などを活用します。情報の裏付けを取ることで、入社後のミスマッチを防げます。
面接は企業を見極める重要な機会です。「月間平均残業時間は具体的に何時間ですか?」「直近3年間の離職者数と理由を教えていただけますか?」「産休・育休からの復職率はどのくらいですか?」「1日あたりの処方箋枚数と薬剤師の配置人数は?」「昇給の実績を具体的な金額で教えていただけますか?」など、具体的に質問しましょう。曖昧な回答しか得られない場合は、情報公開に積極的でない可能性があります。
ステップ3
内定を得た後、必ず内定通知書、労働条件通知書、雇用契約書で条件を確認しましょう。面接で話した内容と相違がないか、給与の内訳(基本給、各種手当)、勤務時間、休日、試用期間の有無と条件、昇給・賞与の規定などをチェックします。記載内容に疑問があれば、必ず確認してから契約しましょう。
薬剤師専門の転職エージェントの活用
薬剤師専門の転職エージェントは、離職率の低い職場を見つける強力なパートナーです。非公開求人へのアクセス、職場の内部情報(離職率、人間関係など)の提供、条件交渉の代行、面接対策・履歴書添削のサポート、入社後のフォローなどのメリットがあります。複数のエージェントに登録(2~3社が目安)し、自分の希望条件を明確に伝え、定期的にコミュニケーションを取ることで、より良い求人に出会える可能性が高まります。
まとめ
薬剤師の離職率は医療・福祉業界で14.6%、薬剤師に限ると約10%と、他職種と比べて特別高いわけではありません。しかし、職場の種類や規模によって離職率には大きな差があります。長く働ける職場を選ぶには、離職率だけでなく、給与体系、勤務条件、育児サポート、キャリアパスなど多角的な視点での評価が重要です。
本記事で紹介したチェックポイントと実践ステップを活用し、自分に合った職場を見つけましょう。転職は人生の重要な決断です。十分な情報収集と慎重な判断で、充実したキャリアを築いてください。
まずはキャリアの可能性を知る相談から
キャリア相談・面談依頼はこちらから
田井 靖人
2013年摂南大学法学部を卒業後、不動産業界で土地活用事業に従事。
2019年から医療人材業界へ転身し、薬剤師と医療機関双方に寄り添う採用支援に携わる。
現在は薬剤師が“自分らしく働ける環境”を広げるべく、現場のリアルやキャリアのヒントを発信。 座右の銘は「人間万事塞翁が馬」。どんな経験も糧に変え、薬剤師の未来を支える言葉を届けている。